黒い樹の器と職人の話 * 7
「妾は大変疲れた。寝る」
大巫女は宣言しました。
「寝るってどこで寝るの」
「ここで寝る」
「それは私の布団だよ」
「妾が寝る」
職人は寝床を取られてしまったので、彼女が寝ている間彼女が帰るべき場所を見に行ってみることにしました。
僕の部屋なんだけどなあ、と思いましたが、女の子を床に寝かせるわけにも行かないし。
割と紳士的な職人でした。
「大巫女さまはいらっしゃいません」
古い力を扱う巫女の一人は言いました。
それは知ってる、とは言わず、職人は問いを一つ口にしました。
「大巫女ってどんなものなのか、教えてくれないか」
「大巫女さまは私たちの力の象徴です」
巫女は答えました。
「あの方がお持ちの大きな力と深い知恵が、私たちが持つ力が役立つものだと証明してくださるのです」
「言い換えれば、我々だけでは満足な力は扱えないということだ」
いきなり話に入ってきたのは集まりの中の一人でした。
職人を迎えた巫女が眉を顰めるのが見えましたが、話に入ってきた男は続けます。
「力を持つ大巫女さまにはその有用性を、
この土地の新しい主にお見せ頂かなければなりません。
そして我らのしていることの意味を理解してもらい、協力してもらわねば」
突然そんなことを言われてきょとんとする職人でしたが、考える間もなくまた別の声が響きました。
「何を言うか、そういう考え方が力の衰えを招くのだ!」
先程とは別の男が憤りを隠そうともせずに言います。
すると最初に話に入ってきた男は、片眉を上げて返しました。
「現実を見つめた方が良い。力の点で見ても権力の点で見ても、王族のために働くのは有益だぞ」
「古い力を持つ大きな生き物たちを滅ぼしたのは王族だぞ!」
どうやら古い力を扱う人々も、一枚岩とはいかないようです。
王さまの息子という目に見える新しい主が現れたことで、
神さまの頃からの古い力――職人にはよく分からないものですが――についての立場が揺らいできたのでしょうか。
「大巫女さまには旗印になっていただかなければならない、王族に相対する私たちの」
「大巫女さまには仲介者になっていただかなければならない、新しい力と古い力の」
違った立場の人々の中でも、少なくとも大巫女だけは大きな力を持つものとして指針になりうるもの。
大巫女が昨夜のことを隠そうとした理由がわかったような気がしました。
先程の人々のあの様子では、
大巫女そのものである面紗が失われたと分かれば余計な混乱を招きそうです。
互いに譲らない人々を後に、職人はこっそりと部屋に戻りました。

部屋に入ると、大巫女は寝床の上で丸くなって眠っていました。
顔に髪が掛かって苦しそうだったので払ってみましたが、起きるそぶりも見せません。
どうやら本当に疲れ切っていたようです。
職人は座布団を並べると、自分はその上に寝転がりました。
*
目を覚ますと、大巫女に掛かっていたはずの布団が自分の上に掛かっていました。
不思議に思って辺りを見回すと、大巫女はもう目を覚まして部屋の隅でごそごそ動いています。
何をしているのかと覗き込もうとすると、
それより先に大巫女が振り向いて、声をかけてきました。
「これを作ったのはお前なのか」
彼女の手元には、職人がここに来てから手慰みに作っていた小鳥の置物が並べられていました。
色々の仕草をする小さな姿は、そう精魂こめて作ったわけではありませんでしたが、
大巫女は部屋の隅に転がっていたものを残らず集めてきていました。
「気に入った?」
職人が微笑むと、大巫女は否定も肯定もせず彼を見つめました。
そして言いました。
「妾もこれを持っている。お前だったのだな」
木でできた小鳥の羽を撫でる彼女の表情が、少しだけ和らいだようです。
社に献上したものの中の一つでしょうか。
時計、窓枠、皿などなど、皆で色々作ったような覚えはありますが、
個人で持っているというようなものは―――
職人が一瞬考え込むと、大巫女は彼のことを面白そうに眺めました。
そして言いました。
「鏡だよ。最初に妾がここに招かれたとき、王の息子の奥方がくれたのだ。良いものだったよ」
そのときのことを思い出しているのか、ちょっと懐かしそうに言う彼女に、
職人は違和感を覚えました。
「もしかして、例のお嫁さんと結構知り合い?」
大巫女は職人の言葉に少しだけ目を見開いて、そしてそのまま伏せ目がちに頷きます。
「よく話し相手になってくれた。
妾はあまり外に出ないように言われていたから、部屋まで訪ねてきて……
あの娘が自分で動けなくなるまでは」
妾とて本当は助けてやりたい、と小さな小さな声で言う彼女を、
職人はただ黙って見つめるしかありませんでした。
*
さて、大巫女はしばらくするとまずいことを口走ったと思ったらしく、
軽く咳払いをすると無理やり横柄な様子で職人のほうに話を回してきました。
「よいか、お前が作ったものは役に立つのだ」
いきなりそんなことを言われても、職人としては意味がわかりません。
「役に立たないのだと言われたら傷つくけど」
「役立つと言ってもただ言葉その通りの意味ではない」
大巫女によると、彼女の持つ鏡や広間の時計を鑑みるに、
職人の作ったものは作った職人自身や持ち主の気持ちを感じ取って、
なんとなく相手の望む働きをするようになるのでした。
「心当たりが無いか?」
「よく分からない」
「まあ、日常生活で使うものなら偶然の範囲内だろうな」
見ておいで、 と彼女は言うと、木の小鳥一羽を手の甲に乗せ、そのままつい、と手を掲げました。
すると驚いたことに、木の小鳥がふわりと浮き上がり、空中をあちらへこちらへと移動し始めたのです。羽が動くようにはなっていない一羽でしたが、心なしか羽ばたいているようにすら見えました。
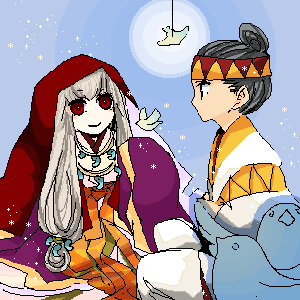
「普通ならばまじないをひとつふたつ唱えなければこういうことは出来ない」
「普通は唱えても出来ないよ」
「妾の話だ」
大巫女はふふんと笑いました。
「妾たちの言葉でいえば、お前の手を通すことで素材に念がこもりやすくなるのだな」
「…だから今回僕が選ばれたのか」
職人は完全に大巫女の言葉を飲み込んだ訳ではありませんでしたが、感慨深げに呟きました。
もともと大きい力のやり取りをしている黒い樹という素材を、
彼が扱うすることで人の力の器になるよう変えるのです。
「妾に付いておいで」
大巫女は言いました。
「黒い樹と話せる場所まで、一緒に連れていってやろう。
でも、それ以上は助けてあげられないぞ。
妾には妾のすることがあるし、黒い樹の身体を手に入れるなんて、大巫女としては許せないことだからな」
心なしか固い表情で言う大巫女の言葉に、職人も神妙な顔で頷きます。
二人は夜を待ちました。