黒い樹の器と職人の話 * 11
「……大巫女……さま?」
職人が少し迷ってから声を掛けると、少女はぴくりと震えました。
疑問形になってしまったのは、彼女の格好が今までと違っていたからです。
幾重にも重ねられた豪華で鮮やかな着物ではなく、薄い衣を一枚身に纏っただけで、
一回りも二回りも小さくなってしまったように見えました。
振り向かない相手にまさか人違いかと職人が悩み始めたところで、
大巫女はゆっくりと顔を上げます。
そして泣き濡れて真っ赤になった目で職人を見止めると、唇を慄かせました。
どうしてここにいる、とかそんなことを言いたかったようです。
「黒い樹を一目見てから帰ろうと思って……」
職人は大巫女に歩み寄りました。自分のことを見ている彼女に手を差し伸べて、立ち上がらせようとしましたが、彼女はそれをとろうとはしませんでした。
何かを大事そうに抱えたまま、小さく固まったように座り込んでいます。
―――やっぱり。
職人は屈み込むと、大巫女の小さな手を開かせて尋ねました。
「やっぱり、これでは受け入れられないと言われた?」
職人の言葉に、大巫女の目が大きく見開かれました。
そこからまた涙がぽろぽろと零れ始めます。
「違う……私が……」
妾ではなく私と言ったその少女には、以前のような偉そうな、あるいは偉そうであろうと努力した、そんな面影はありません。
彼女の手の中にあったのは幾枚かの布の切れ端のようなものでした。
良い生地で出来ているようでしたが、何かに引き裂かれたようにぼろぼろに破け、
元がどういう形をしていたのかも図りづらいようなもの。
黒い樹の中から戻ってくるときに、黒い樹の欠片によってずたずたにされてしまった、
大巫女の証である大事な面紗でした。
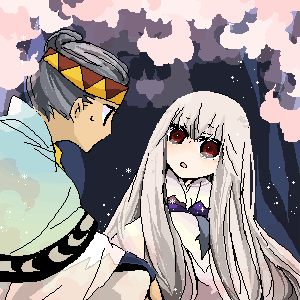
「皆に謝りに行こうと思ったのに、怖くてどうしても出来なかった」
面紗がこうなってしまっては、古い力を扱う人々に崇敬されてきた大巫女という存在は
もう滅びたも同然でした。
小さな頃から大巫女になるために育てられてきた彼女は、大巫女でなくなることも、面紗がもはや面紗たりえないことを知って人々が失望するのを見るのも、怖くてたまらなかったのです。
本当は皆にこの事態を説明しなければならないのに、そのやるべきことがどうしても出来ません。
どうして良いか分からなくなった彼女は、一度自分の部屋には戻ったものの、大巫女の衣装も何もかも置いて出てきてしまったのです。
そして全ての始まりである黒い樹の下に来て泣いていたのでした。
「……皆に合わせる顔が無い。
只でさえ我々は揺れているのに、取り返しのつかないことをしてしまった」
面紗だったものを抱き締めながらぽつぽつと言う大巫女に、職人は言いました。
「あなたのせいじゃない、僕が巻き込んだんだ」
職人の言葉に、少女は顔を膝に埋めたまま小さく首を振りました。
「それでも、これを守らなかったのは私だ」
彼女が好きで協力したといえばそれで通るのかもしれませんが、
職人にはとてもそんな風には考えられませんでした。
それでなくとも力無く項垂れている少女はひどく弱弱しく見え、
見ているこちらの胸まで痛くなってきます。
だから職人は言いました。
「帰れないなら僕と一緒にここを出よう。
黒い樹の器を作るのを、手伝って欲しい」
*
「忘れ物は無いですか?」
王さまの息子の使者の男は、さわやかに尋ねてきました。
しかし職人の後ろにくっついている少女を目にしてちょっと顔を引きつらせました。
「…………」
「……色々あって……」
「……色々ですか……」
「黒い樹のことをよく知ってる人なんだ」
慌ててそう言った職人ですが、その前に使者の男は顔色を戻して頷いたのでどう思われたかは分かりませんでした。
大巫女だった少女はぺこりと頭を下げ、顔を隠すように俯いていました。
使者の男は少女を馬車の中へ案内し、職人のことも促し、そして自分は御者の隣に座りました。
そして、「あ、そうだ」と職人を呼びました。
職人はちょっと困ったような顔で使者の男のところへ行きました。
多分呼ばれたのは、ちょっとした話をするためではないだろうと思ったからです。
「誘拐は駄目ですよ」
「僕もそう思う」
「誘拐じゃないんですか?」
そう言われると職人は困りました。相手はここから出ることを同意したのですが、正常な精神状態とは言いがたいからです。
「私とて相手が相手でなければこんなことは聞きません、が」
使者の男はそんな風に言いました。
「あれは――どなたですか?」
「当ててみるかい?」
職人が肩をすくめて言うと、使者の男は突然言いました。
「王宮には王族専属の占い師がいます。その占いはほぼ確実に当たるという占い師が」
「―――?僕について占ったっていう?」
怪訝そうな顔の職人に、使者の男は頷きます。
「そうです。王族に何かが起こるとき、その言葉を皆は頼りにしています。
主と私たちがこちらに移ってくるときにも、占い師の言葉を幾つか貰いました。
占い師が言ったのはこうです―――
古い力を扱う者たちとの関係は大事だ、と」
職人は背筋に冷たいものを感じました。
使者の男の目は鋭く、口調は丁寧であっても微笑みはありません。
もしここで行方不明の大巫女を古い力を扱う彼らに差し出せば、
使者の男は彼らの感謝の意を得られるでしょう。相手の中で揉めていたらしい王族への対応についても、友好的なほうに傾くかもしれません。
高みから見下ろしてくる相手から目を逸らさずに、職人は尋ねました。
「もしも彼女が、古い力を扱う彼らにとって重要な人物だったら、あなたはどうするんだ?」
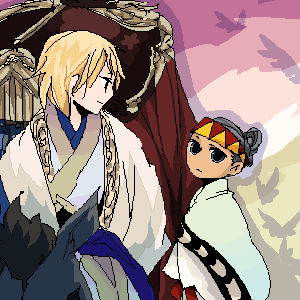
それから数秒間睨み合いのような対峙が続きましたが、
使者の男が小さく息を吐くと、幾分表情を和らげました。
「何もしません」
「えっ?」
「彼女の合意があればの話ですが。もちろんこちらに火の粉が掛からないようにはしますよ」
私は何も見なかった、と言うように、使者の男は目を瞑りました。
「でも、あちらと仲良くなるチャンスなのに」
「そうなんですがね」
王宮で、東の土地に移っていく彼らを前に、占い師は言いました。
東の土地には古い力を扱う人々がいます。彼の地では一目置かれる存在でしょう。
彼らとの関係はあなたたちにとって大事です―――彼らに飲まれてはいけませんよ。
「私たちは彼らを凌駕しなければなりません」
使者の男は言いました。
「古い力を扱う者たちですが、実際に警戒すべき力を持つのは大巫女くらいのもの。彼女がいなくなれば確実に衰退します。
仲良くしていくのも良いですが、どちらかと言うと叩き潰すのが最初の王さまのやり方でね」
使者の男はうっすらと微笑むと、馬車の中に入るようにと職人を促しました。
「主はそういうやり方がお好きな方ではありませんが」
なかなかのんびりした方ですから、と扉を閉める職人の後ろから声がしました。
「少しあなたに似ているかもしれませんね」