常世の織物と旅人の話 *5
「旅人さんはどこに行くの?」
ある日、少女は旅人さんに尋ねました。
冬にしては暖かな日で、丘の上には緩やかな風が吹いています。
「どこっていうのは、特にないねえ」
基本的に外を見るのが目的だし、と彼は雲を見上げます。
「じゃあ、この街に長く居られるの?」
「うーん……僕と相性がよければだけど」
旅人さんはちょっと口ごもりました。
「ちょっと探したいものがあるんだよね」
「何?それって何?」
はぐらかされそうな雰囲気になったので、少女は急いで尋ねます。
「……」
旅人さんは首の後ろに手を回したまま何ごとか考えている様子でしたが
不意に少女を呼んで自分の後ろに回らせました。
「見てごらん」
そして、首の付け根、だいぶ背中よりのところまで、自分の服を引き下げます。
覗き込んだ少女はそこを見つめて、暫くした後尋ねました。
「これは、あざ?」
「そう」
旅人さんの首の付け根にあったのは、半円型に近い小さなあざでした。
「うちの両親にもあってね……二人のあざを組み合わせると、ひとつの花の模様みたいになるんだよ」
「わあ」
なんだか少女にはロマンチックに響く話です。
「僕にもそういう人が居ないかなと思って」
うちの村過疎だし、長男の僕がお嫁さんを連れて行かないとね。
少々照れくさくなったらしく、旅人さんは肩をすくめて少女に笑いかけました。

少女はちょっとがっかりしました。自分の体と付き合ってきて十数年、
そんなあざを見かけたことはついぞありません。
しかしまあとりあえず旅人さんを助けよう精神で、お嫁さん探しを考えることにしました。
「旅人さん、そのあざをよく見せて」
「ええ?どうしたの?」
「その模様をお菓子に焼きいれるのよ。
そうしたら、同じ模様を持っている人が見つかるかもしれないわ」
少女が帰宅して両親に思い付きを話すと、両親はまず心配しました。
娘がなんだか得体の知れない旅人に引っかかっていたからです。
しかし彼らは新しい試みが好きでしたし、新商品も出したいところだったので、
考えていた小さな焼き菓子に模様を焼き入れてみることにしました。
*
それから十数日が過ぎ、王都では3日後に迫る年越しの祭のための準備が着々と進められていました。
そんな中、件の織物の調べは停滞していました。
専門家などを呼んでみましたが、織物がどの地方で作られたものかとか、
似たようなものが見つかっていないかとか、判明したことはほとんどありませんでした。
「あまり見かけない糸ですし、似たような地形の場所もいくつかあたっていますが、
なかなか候補も見つかりません」
「しかし織り方や色あわせなどは様々な地方のものを取り入れているようです。
様々な地方を渡り歩いて習得したものか、もしくは」
「すべてが集まってくる王都で見知ったものではないかと」
口々に意見を述べる人々ですが、やっぱり事態は進展しません。
「あと、例の娘の正体につきましても不明のままです」
「まったく蜃気楼か何かのように掴めない話だ」
王さまは不機嫌そうに言いましたが、
何がしかの試練はつき物と諦めている様子でした。
そして、何の気なしに目を織物の方へ向け―――
「ん」
首を傾げました。
「お前たち、この模様は何だ」
専門家たちが覗き込むと、それは織り込まれた小さな家の上にある、やはり小さな模様のようなものでした。
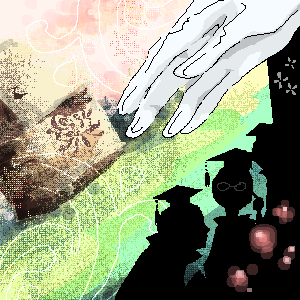
「どうやら花のように見えるのですが」
専門家の一人は言いました。
「我々も見かけたことのない柄なのです」
「どこかの伝統の柄とかではないというわけだな」
「はい」
王さまはその返事にまた訝しげな表情を見せます。
「……だが、わたしはどこかで見た気がするぞ、このような」
王さまは何かを思い出そうとするように窓を見やりました。
「割と最近のことだったと思うのだが―――」
*
同じ頃、丘の上を転がるように駆ける少女の姿がありました。
「旅人さん聞いて聞いて!」
「やあ久しぶりだね?ずいぶん急いでるけど、何かに追われてるのかい」
「違うわよ!」
少女は興奮のあまり手をぶんぶんと振りながら喋りました。
「模様をつけたお菓子が売れたの!」
「売れたの?」
「そうなの!あのね、半分ずつの、何種類かの花の模様にして売ったのよ。
そうしたらね、王都の中で結構評判になったの」
年末までのひと月は色々とイベントが多く、
新しいお菓子はちょと人目を引いたのでした。
恋人同士のイベントが多かったのも、
半分ずつの模様という性質上、良かったのかもしれません。
もともと味には定評のあったパン屋のこと、口コミで多くの人々が買い求めるようになったのです。
嬉しい話でしたが家の手伝いも忙しくなり、なかなか旅人さんを訪ねられなかった少女でした。
少女が旅人さんにそのお菓子を渡すと、彼は感心したように眺めます。
半月形をした、ちょっと歯ごたえもありそうな可愛らしい焼き菓子でした。
「それでね、年越しの祭の屋台の出し物に加えてもらえることになったの」
「お城であるってやつだね」
「それの中にもね、お祭用に祝福してもらったお砂糖が入ってるの」
「そういわれると何かすごい感じがするね」
旅人さんはちょっと好奇心をそそられたようです。
「お祭には遠くからの人や頭のいい人も来るから、旅人さんの待ち人も現れるかもしれないよ」
それはそんな必死に探してくれなくても大丈夫だよ、と旅人さんは言いましたが、
お菓子も売れて助かっていることだし、少女は旅人さんに何かしなければならないと思いました。
それに、そう、そうだ。お祭って確か。

「旅人さん、一緒にお祭に行かない?」
少女は意気込んで言いました。
「甘いものもたくさんあるし、王さまも居るし、花火も上がるのよ」
後者二つにはそれほど興味はわかなかったようですが、旅人さんは少女と一緒にお祭に行くことになりました。